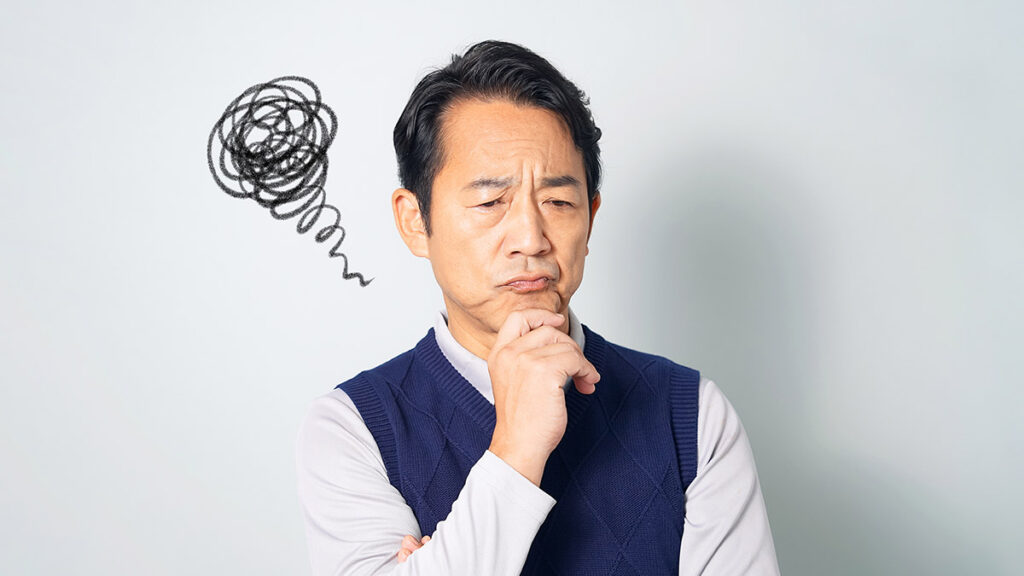マナー・作法
【すぐ使える】忌引きメールの例文とテンプレート|状況別の文例付き
- マナー・作法
- 参列者
- 葬儀・葬儀後
2025年10月17日

身内の不幸という突然の出来事に直面したとき、悲しみの中で会社や学校への連絡をどのように行うべきか迷われる方は少なくありません。忌引きメールは、相手に失礼のないよう配慮しながら、必要な情報を正確に伝える重要なコミュニケーション手段です。この記事では、上司・同僚・取引先・学校など、さまざまな相手に応じた忌引きメールの例文とテンプレートを状況別にご紹介します。忌引きメールの基本的なマナーから、避けるべき表現、送信後のフォローアップまで、実践的な情報を網羅的にお伝えしますので、急な状況でも安心して適切な連絡ができるようになります。
忌引きメールの基本マナーと書き方の原則
忌引きメールを作成する際には、いくつかの重要な原則とマナーがあります。突然の訃報で動揺している状況でも、これらの基本を押さえることで、相手に失礼なく必要な情報を伝えることができます。まずは忌引きメールの基本構成と、メール連絡が適切な場面について理解しましょう。
忌引き連絡はメールでも問題ないのか
忌引きの連絡は原則として電話や直接の口頭連絡が望ましいとされていますが、状況によってはメールでの連絡も許容されます。特に深夜や早朝に訃報を受けた場合、相手の業務時間外である場合、直属の上司が不在である場合などは、まずメールで連絡を入れ、後ほど電話でフォローするという方法が実用的です。近年ではリモートワークの普及もあり、メールでの忌引き連絡も一般的になってきています。ただし、可能な限り電話での連絡を優先し、メールは補足的な役割として活用することが推奨されます。
メールで連絡する場合でも、送信後に電話で直接話す機会を設けることで、より丁寧な印象を与えることができます。また、会社の規定によっては忌引き休暇の申請に正式な書類提出が必要な場合もあるため、メール送信後に人事部門への確認も忘れないようにしましょう。
忌引きメールに必ず含めるべき項目
忌引きメールには、相手が状況を正確に把握できるよう、必要最低限の情報を明確に記載する必要があります。件名には「忌引き休暇のご連絡」や「忌引きによる休暇取得のお願い」など、一目で内容が分かる表現を使用しましょう。本文には、故人との続柄、死亡日時、休暇を取得する期間、葬儀の日程(分かる範囲で)、緊急時の連絡先を必ず記載します。
業務に関する情報も重要な要素です。現在担当している業務の状況、引き継ぎ先の担当者名、不在中の連絡体制などを明記することで、職場への配慮を示すことができます。ただし、詳細な葬儀の場所や家族の個人情報など、必要以上にプライベートな情報を記載する必要はありません。簡潔かつ必要十分な情報提供を心がけましょう。
避けるべき忌み言葉と不適切な表現
忌引きメールでは、使用を避けるべき表現がいくつか存在します。「重ね重ね」「たびたび」「ますます」などの重ね言葉は、不幸が繰り返されることを連想させるため使用を控えます。また「再び」「引き続き」「追って」なども同様の理由から避けるべき表現です。数字では「四」や「九」は縁起が悪いとされるため、日程を伝える際には「4日間」ではなく「四日間」または「3日から5日まで」といった表現に変更しましょう。
宗教的な配慮も重要なポイントで、「ご冥福をお祈りします」「成仏」「供養」などの表現は仏教特有のものであり、キリスト教や神道の場合には適切ではありません。相手の宗教が不明な場合は、「哀悼の意を表します」「心よりお悔やみ申し上げます」など、宗教色のない表現を選ぶことが安全です。また、絵文字や顔文字の使用は厳禁で、ビジネスメールとしての礼儀を守ることが大切です。
【相手別】忌引きメールの例文とテンプレート
忌引きメールは送る相手との関係性によって、適切な文体や内容が大きく異なります。ここでは、上司、同僚、取引先、学校など、主要な連絡先ごとに具体的な例文とテンプレートをご紹介します。それぞれの状況に応じてカスタマイズしてご活用ください。
直属の上司への忌引きメール例文
直属の上司への連絡は、忌引き休暇取得において最も重要なコミュニケーションです。上司には業務の引き継ぎや今後の対応について具体的に伝える必要があります。以下のテンプレートを参考に、自身の状況に合わせて調整してください。
件名の例としては「忌引き休暇取得のご連絡とお願い」「忌引きによる休暇のご報告」などが適切です。本文では、まず訃報を伝え、次に休暇期間と業務の引き継ぎについて明確に記載します。具体的な例文は以下の通りです。
| 項目 | 記載内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 件名 | 忌引き休暇取得のご連絡 | 簡潔明瞭に状況を伝える |
| 冒頭 | お疲れ様です。突然のご連絡で申し訳ございません | 謝罪の言葉から始める |
| 訃報報告 | 本日未明、父が急逝いたしました | 故人との続柄と事実を簡潔に |
| 休暇期間 | つきましては、○月○日から○月○日まで忌引き休暇をいただきたく存じます | 具体的な日程を明記 |
| 業務引き継ぎ | 担当業務については○○さんに引き継ぎを依頼済みです | 対応済み事項を報告 |
| 連絡先 | 緊急のご連絡は携帯電話までお願いいたします | 連絡可能な手段を提示 |
上司へのメールでは、迷惑をかけることへの謝罪と、業務への影響を最小限にする配慮を示すことが重要です。可能であれば、メール送信後に直接電話で報告することで、より丁寧な印象を与えることができます。また、復帰予定日が変更になる可能性がある場合は、その旨も併せて伝えておくと親切です。
同僚や部署メンバーへの忌引きメール例文
同僚への連絡では、業務の引き継ぎや不在中のサポートをお願いする内容が中心となります。上司への連絡よりもやや砕けた表現も許容されますが、基本的な礼儀は保つ必要があります。部署全体に一斉送信する場合と、個別に依頼する場合で若干内容を調整しましょう。
同僚へのメールでは、具体的にどの業務をどのように引き継ぐかを明確に記載することで、不在中の混乱を防ぐことができます。特に進行中のプロジェクトがある場合は、現在の進捗状況、次のステップ、関連資料の保存場所などを詳しく伝えることが大切です。以下に部署メンバー向けの例文を示します。
皆様、お疲れ様です。私事で大変恐縮ですが、祖母が○月○日に他界いたしましたため、○月○日から○月○日まで忌引き休暇をいただきます。
不在中、○○プロジェクトにつきましては現在△△の段階まで完了しており、次回のミーティングまでに必要な資料は共有フォルダの『○○』に保存してあります。
急ぎのご対応が必要な場合は、○○さんにお願いしてありますので、そちらにご連絡ください。
皆様にご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
取引先や社外関係者への忌引きメール例文
取引先への連絡では、詳細な個人情報は控えめにし、業務への影響と代替の連絡先を明確に伝えることが最優先です。社外の方には葬儀の詳細などプライベートな情報を細かく伝える必要はありませんが、対応が遅れる可能性がある案件については具体的に説明しましょう。
取引先へのメールでは、プロフェッショナルな印象を保ちながらも、必要な配慮をお願いする姿勢が重要です。件名は「不在のご連絡」や「休暇取得のお知らせ」など、ビジネスライクな表現を使用します。本文では、休暇期間中の代理担当者の連絡先を必ず明記し、取引先が困らないよう配慮しましょう。
株式会社○○ △△様、いつも大変お世話になっております。
私事で恐縮ですが、身内に不幸があり、○月○日から○月○日まで休暇をいただくこととなりました。
つきましては、この期間中のお問い合わせやご連絡は、弊社の○○(メールアドレス、電話番号)までお願いできますでしょうか。
ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
復帰後、改めてご連絡させていただきます。
学校や教育機関への忌引きメール例文
学校への連絡では、保護者から担任教師や学校事務へメールを送るケースと、学生本人が大学の教授や事務局へ連絡するケースがあります。いずれの場合も、欠席期間と忌引き証明書の提出について言及することが重要です。小中高校の場合は保護者から、大学の場合は学生本人からの連絡が一般的です。
学校への連絡では、授業や試験への影響、課題の取り扱いについても確認が必要です。特に試験期間と重なる場合は、追試験の手続きなどについて早めに相談しましょう。以下に大学生が教授へ送る例文を示します。
○○先生、お世話になっております。
○○学部○年の△△です。
私事で大変恐縮ですが、祖父が○月○日に他界したため、○月○日から○月○日まで忌引きで欠席させていただきます。
この期間は○○の授業と重なっておりますが、復帰後に配布資料をいただくことは可能でしょうか。
また、忌引き証明書は後日学生課へ提出いたします。
急なご連絡となり申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
相談員が待機しています。
最短30分でお迎えに伺います。
ご葬儀のご依頼・ご相談はこちら
0120-43-5940
- 通話無料
- 相談無料
- 24時間365日対応
忌引きメールの件名の書き方と重要性
件名は受信者が最初に目にする情報であり、メールの内容を即座に理解してもらうための重要な要素です。特に忌引きメールの場合、緊急性と重要性を適切に伝える件名を設定することで、相手が優先的に確認し、適切な対応をとってくれる可能性が高まります。
効果的な件名の具体例と構成要素
忌引きメールの件名には「忌引き」という言葉を明確に含めることで、受信者が内容を一目で理解できるようにすることが最も重要です。曖昧な表現や間接的な言い回しは避け、ストレートに状況を伝える件名を選びましょう。効果的な件名の例としては「忌引き休暇取得のご連絡」「忌引きによる休暇のお願い」「忌引き休暇のご報告」などがあります。
件名に日付や期間を含めることも有効です。例えば「【○月○日〜○日】忌引き休暇のご連絡」とすることで、不在期間が件名から把握できます。ただし、件名が長くなりすぎるとスマートフォンなどで表示が途切れる可能性があるため、30文字以内に収めることを推奨します。また、【重要】や【緊急】といった記号を冒頭に付ける方法もありますが、使用は慎重に判断しましょう。
相手別の件名の使い分け方
送信相手によって、件名の表現も微妙に調整する必要があります。直属の上司には「忌引き休暇取得のご相談」や「忌引き休暇のお願い」など、許可を求めるニュアンスの件名が適切です。一方、同僚や部署メンバーには「忌引き休暇のご連絡」や「不在のお知らせ(忌引き)」など、情報共有を主眼とした件名が自然です。
取引先や社外の関係者には、やや控えめな表現として「休暇取得のお知らせ」や「不在期間のご連絡」とし、本文で詳細を説明する方法も選択肢の一つです。ただし、業務への影響が大きい場合は「忌引き休暇による不在のご連絡」と明確に記載する方が誠実です。学校への連絡では「忌引き欠席のご連絡(○年○組 氏名)」のように、学年・クラス・名前を含めることで、受信者が即座に識別できるよう配慮しましょう。
件名で避けるべき表現とNG例
件名において避けるべき表現には、曖昧すぎる表現や軽い印象を与える表現があります。「お休みのお知らせ」「ちょっと休みます」「欠席します」などの表現は、忌引きという重要な理由が伝わらないため不適切です。また、「大変なことになりました」「困っています」など感情的な表現も、ビジネスメールとしては相応しくありません。
記号の過度な使用も避けるべきです。「!!!」や「※※※」などの記号を多用すると、かえって軽薄な印象を与えてしまいます。また、全角英数字や不要なスペースの使用も、プロフェッショナルな印象を損なう要因となります。件名は簡潔かつ明確に、そして礼儀正しく、という原則を守ることが大切です。
忌引きメール送信後のフォローアップと対応
忌引きメールを送信した後も、いくつかの重要な対応事項があります。適切なフォローアップを行うことで、職場や学校との良好な関係を維持し、復帰後のスムーズな業務再開につなげることができます。ここでは、メール送信後に注意すべきポイントと具体的な対応方法をご説明します。
メールへの返信が来た場合の対応方法
忌引きメールへの返信として、お悔やみの言葉や励ましのメッセージをいただくことがあります。このような返信には、簡潔なお礼の言葉を返すことが基本的なマナーですが、過度に丁寧な対応は不要です。相手に気を遣わせないよう、短い文面で感謝の気持ちを伝えましょう。
返信メールには「返信不要」の旨を明記することで、相手が再度返信する負担を軽減することができます。例えば「温かいお言葉をいただき、誠にありがとうございます。ご返信は不要でございますので、よろしくお願いいたします」といった表現が適切です。特に葬儀の準備などで忙しい状況では、メールのやり取りを最小限にすることも重要な配慮です。
休暇期間の変更が必要になった場合の連絡
葬儀の日程変更や予期せぬ事態により、当初連絡した休暇期間を延長または短縮する必要が生じることがあります。このような場合は、できるだけ早く関係者に再度連絡を入れることが大切です。メールの件名には「【変更】忌引き休暇期間のご連絡」など、変更があることを明示しましょう。
変更連絡のメールでは、変更の理由を簡潔に説明し、新しい休暇期間を明確に記載します。また、業務への影響や追加の引き継ぎ事項がある場合は、それらについても言及します。「先日ご連絡いたしました忌引き休暇の期間について、葬儀日程の都合により、○月○日までの延長をお願いしたく存じます。度重なるご連絡で申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします」といった表現が適切です。
復帰時のお礼メールと挨拶の方法
休暇から復帰した際には、サポートしてくれた上司や同僚、取引先へのお礼の連絡を忘れずに行いましょう。復帰初日または前日に、関係者へお礼のメールを送ることがマナーです。件名は「復帰のご挨拶とお礼」や「業務復帰のご報告」などが適切です。
復帰メールでは、休暇中のサポートへの感謝を表明し、今後の業務への意欲を示すことが重要です。「この度は忌引き休暇を取得させていただき、誠にありがとうございました。不在中、業務をサポートいただきました皆様に心より感謝申し上げます。本日より通常業務に復帰いたしましたので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします」といった内容が基本的な構成です。取引先には、個別に復帰の連絡と今後のスケジュール調整の提案を行うと丁寧です。
状況別の忌引きメール実践ガイド
忌引きが必要となる状況はさまざまで、それぞれに応じた適切な対応が求められます。ここでは、よくある具体的なシチュエーションごとに、実践的なメール作成のポイントと注意事項をご紹介します。自身の状況に最も近いケースを参考に、適切な連絡を行いましょう。
深夜や早朝に訃報を受けた場合の対応
深夜や早朝に訃報を受けた場合、すぐに電話で連絡するのは相手の迷惑になる可能性があります。このような状況では、まずメールで第一報を入れ、相手の業務時間になってから電話でフォローするという二段階の連絡方法が推奨されます。メールには「早朝のご連絡となり申し訳ございません」といった一文を添えることで配慮を示しましょう。
深夜・早朝のメールでは、「本メールを確認されましたら、追って電話にてご連絡させていただきます」と記載することで、後の電話連絡への準備ができます。また、緊急の業務事項がある場合は、その処理方法についても簡潔に記載しておくと、受信者が朝一番で対応を判断できるため親切です。時間帯に配慮した連絡方法を選択することで、礼儀正しい印象を維持できます。
海外出張中や遠方にいる場合のメール
海外出張中や遠方にいる状況で訃報を受けた場合、帰国や移動に時間がかかるため、より詳細なスケジュール情報を伝える必要があります。現在地、帰国予定日時、移動中の連絡手段などを明記し、状況を正確に把握してもらうことが重要です。
海外にいる場合は時差の関係で連絡が取りにくい状況も予想されるため、メールでの連絡が特に有効です。「現在○○国に出張中のため、帰国は○月○日の予定です。帰国後、直ちに必要な手続きを行い、○月○日から忌引き休暇を取得させていただきたく存じます。移動中は携帯電話への国際ローミングが可能ですが、繋がりにくい可能性がございます。緊急の場合はメールでご連絡いただけますと幸いです」といった具体的な情報提供が必要です。
試験期間中や重要なプロジェクト進行中の場合
試験期間中や重要なプロジェクトの進行中に忌引きが必要となった場合、特に慎重な連絡と調整が必要です。学生の場合は、試験の追試験制度や課題提出の延期について、事前に確認できる範囲で情報を収集しておくことが望ましいです。社会人の場合は、プロジェクトの重要なマイルストーンへの影響を最小限にする代替案を提示することが重要です。
重要案件が進行中の場合のメールでは、現状報告と引き継ぎ内容をより詳細に記載する必要があります。「現在進行中の○○プロジェクトにつきましては、□□フェーズまで完了しており、次のステップは△△です。関連資料はすべて共有フォルダに整理済みで、○○さんに詳細を引き継ぎましたので、滞りなく進行できる体制を整えております。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします」といった具体的な情報提供が信頼につながります。
忌引き休暇制度の基礎知識と確認事項
忌引きメールを作成する前に、自身が所属する組織の忌引き休暇制度について正確に理解しておくことが重要です。制度の内容は会社や学校によって大きく異なるため、事前に就業規則や学則を確認しておくことで、適切な日数の休暇申請ができます。
会社の忌引き休暇制度と取得可能日数
忌引き休暇は法律で義務付けられた制度ではなく、各企業が就業規則で独自に定める福利厚生制度です。そのため、会社によって取得可能日数や対象となる親族の範囲が異なります。一般的な目安として、配偶者や父母の場合は7日から10日程度、子どもの場合は5日程度、兄弟姉妹や祖父母の場合は3日程度とされていますが、必ず自社の規定を確認しましょう。
忌引き休暇の日数には、移動日や葬儀の準備期間も含まれることが一般的です。また、有給休暇とは別に取得できる特別休暇として設定されている場合と、有給休暇の一部として扱われる場合があります。給与の支払い有無についても会社により異なるため、人事部門に確認することをお勧めします。遠方の場合や海外の場合は、通常より長い日数が認められることもあるため、特別な事情がある場合は相談してみましょう。
学校の忌引き制度と出席日数への影響
学校における忌引きは「忌引き欠席」として扱われ、通常の欠席とは区別されます。小学校から高校までは、忌引きは出席すべき日数から除外されるため、出席率には影響しません。ただし、忌引き証明書の提出が必要な場合が多いため、学校の指示に従って適切な書類を準備しましょう。
大学の場合は、各大学の学則によって取り扱いが異なります。忌引き欠席が公欠として認められる場合もあれば、通常の欠席と同じ扱いになる場合もあります。試験期間中の忌引きについては、追試験制度が設けられていることが一般的ですが、申請期限や必要書類が定められているため、早めに学生課や教務課へ相談することが重要です。レポート提出期限の延期についても、教授の裁量によるところが大きいため、個別に相談しましょう。
忌引き証明書の取得方法と提出手続き
忌引き休暇を取得した後、会社や学校から忌引き証明書の提出を求められることがあります。忌引き証明書とは、実際に身内の葬儀があったことを証明する書類で、一般的には会葬礼状や葬儀の案内状、死亡診断書のコピーなどが該当します。提出を求められる書類の種類は組織によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
忌引き証明書は、休暇取得の正当性を示すための重要な書類であり、提出期限が定められている場合も多いため、葬儀後速やかに準備することが大切です。会葬礼状は葬儀に参列してくださった方に渡されるものですが、喪主や遺族に依頼すれば追加で入手できます。死亡診断書のコピーを使用する場合は、個人情報保護の観点から、一部を黒塗りにすることが認められる場合もあるため、提出先に確認しましょう。証明書の提出方法は、原本の提出、コピーの提出、写真データの提出など、組織によって異なります。
まとめ
忌引きメールは、悲しみの中でも適切に送る必要がある重要な連絡手段です。この記事でご紹介した例文やテンプレートを活用することで、相手に失礼なく、かつ必要な情報を正確に伝えることができます。メールには故人との続柄、休暇期間、業務の引き継ぎ、緊急連絡先などの必須項目を含め、忌み言葉や宗教的配慮にも注意を払いましょう。
送る相手によって適切な文体や内容は異なります。上司には業務への配慮を示し、同僚には具体的な引き継ぎ内容を、取引先には代替連絡先を明確に伝えることが大切です。メール送信後も、返信への対応や復帰時のお礼など、適切なフォローアップを行うことで、良好な関係を維持できます。
忌引き休暇制度は会社や学校によって異なるため、事前に規定を確認し、必要に応じて忌引き証明書の準備も忘れずに行いましょう。突然の訃報に直面した際も、この記事の情報を参考にすることで、落ち着いて適切な連絡ができるはずです。大切な方との最後の時間を心穏やかに過ごせるよう、必要な手続きは迅速かつ適切に行いましょう。